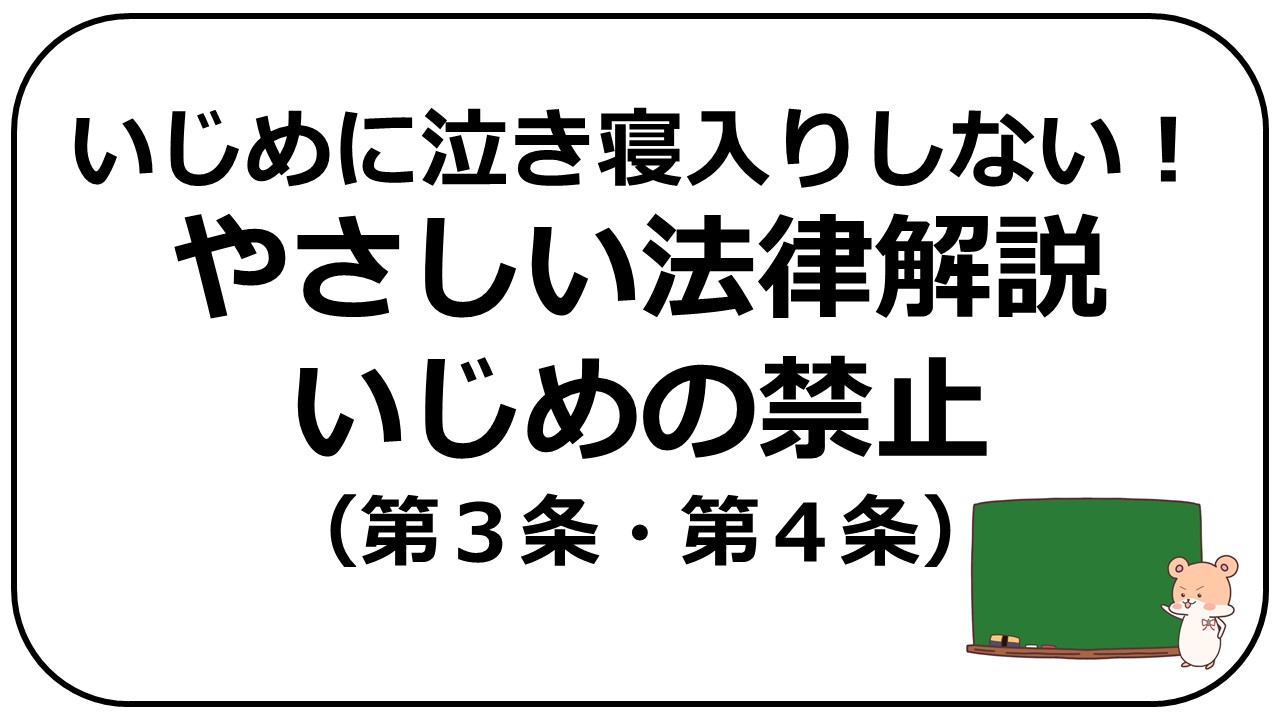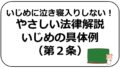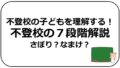はじめに
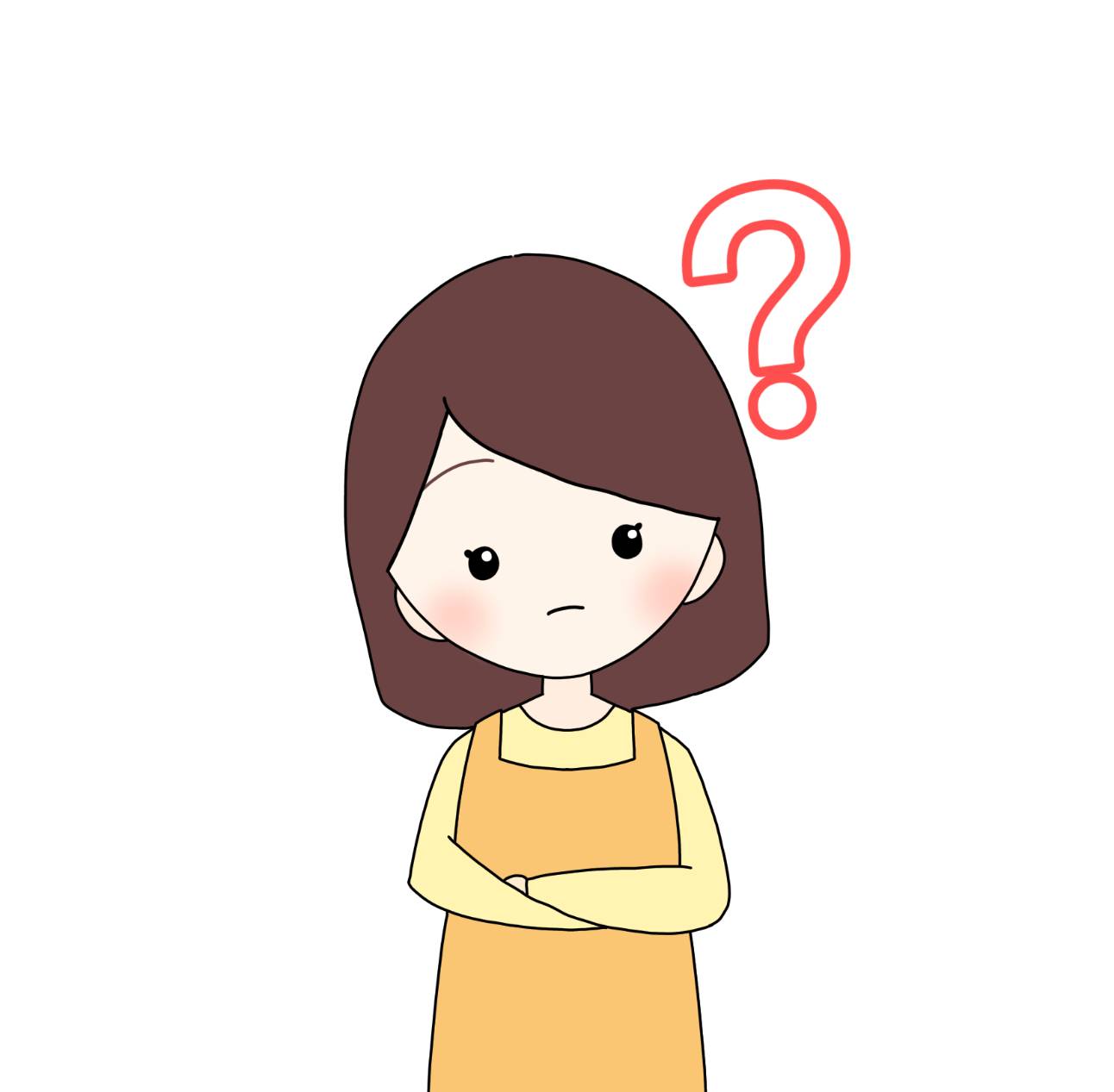
いじめをしてはいけないのは、道徳上の問題でしょうか?

いじめは、法律で禁止されています。いじめ防止対策推進法の第4条です。
もちろん、道徳上も問題となりますが、”法律で禁止されている”意味は重いです。
【条文】(基本理念)第3条
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
【解説】(基本理念)第3条
基本理念を定める意義
本条で定められているのは、基本理念です。そのため、これが直ちに具体的な行動とつながるものではありません。
しかし、いじめ防止等のための仕組みを理解し、運用していく場合には、この基本理念と整合的に行われなければなりません。その点で、この条文は大変重要です。
いじめ防止対策推進法に従って、国・地方公共団体・学校などにおいて、いじめ防止のための方針が定められています。それらの方針が、この基本理念と整合的であるか、常に検証され、見直されていかなければなりません。
第1項 「全ての児童等に関係する」

全ての児童等に関係するという文言の背景には、「多くの児童・生徒がいじめの被害者と加害者の両方を経験する」という認識があるんだな。
さらに、いじめはどの学校にでも、誰の身にも起こりうることで、未然防止・早期発見・対処が必要だという認識に立っています。

これは画期的なことで、今までの「いじめがないのがいい学校」という発想から、「いじめは起こりうるもので、きちんと対応している学校がいい学校」という発想へ転換しています。

現場がどこまでその発想に転換できているかは、学校ごとにグラデーションがあるんだな。
第2項 「いじめを認識しながらこれを放置することがないよう」
「いじめを見て見ぬふりをしている者も加害者である」という意見がありますが、いじめ防止対策推進法では、現実をもっと丁寧に捉えています。森田洋司先生のいじめの四層構造が元になっていますが、「加害者」「被害者」「観衆」「傍観者」の四層にわけて認識します。
加害者:いじめを行っている児童・生徒
被害者:いじめの被害を受けている児童・生徒
観衆:いじめを見て笑っていたり、はやし立てたりしている児童・生徒
傍観者:いじめを見て見ぬふりをしている児童・生徒
そして、いじめの防止等のために「観衆」「傍観者」のあり方が鍵になるのですが、今までは周囲にいる児童等の個人の倫理意識・規範意識に任されてしまっていました。それを改め、いじめの問題に関する児童等の理解を深めることをこの基本理念に定めています。
第3項 連携
いじめ防止等のために、学校現場だけではなく、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者が連携し、社会を挙げて対応することが必要かつ効果的であるという認識を表しています。
この「その他関係者」には、弁護士はもちろん、司法書士、行政書士、また人権擁護委員会、児童福祉関係者、保健師、学校医などが例としてあげられています。
また、衆院文部科学委員会の付帯決議(※法律可決の際、付け加えられる委員会の意思)では、「教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守り通す責務を有するものとして、いじめに係る研修の実施等により資質の向上を図ること」とされています。社会全体でいじめ問題を解決していくのですが、まずは教職員にその責務があるということです。

学校だけで抱え込まない、でもいじめ解決の中心には学校の先生がいるということですね。

不登校への対応とも似ているんだな。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337280.htm
文部科学省 別添4 いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議 (衆議院文部科学委員会)
【条文】(いじめの禁止)第4条
第4条
児童等は、いじめを行ってはならない。

シンプルな条文ですね

はい。とても大切な条文です。
いじめが”法律で”禁止されていることは、児童・生徒への指導のしやすさにもつながります。
【解説】(いじめの禁止)第4条
この条文は、成立過程で1点だけ議論がありました。それは、「児童等は」という文言を入れるのか入れないのかという議論です。児童に限定した文言を入れると、「では、大人はいじめをしてもいいのか」「教職員はどうなんだ」という話が出てくるからです。

稚拙な議論にも思えるけど、こういった細かな配慮がいるんだな。

教員によるいじめはあってはならないもので、あえて法律に禁止と書く必要はないという結論になりました。
もちろん、過去には教員がいじめの加害者となったり、いじめを助長したケースは多々あります。
この点、法律には書かないが、さきほど出てきた付帯決議で、「教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守り通す責務を有するものとして、いじめに係る研修の実施等により資質の向上を図ること」と書いておくことで、教員によるいじめがないように配慮しています。

教員による体罰は別の法律で禁止されているんだな。
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。

次回は、国・地方公共団体・学校の設置者の義務について解説しますね。