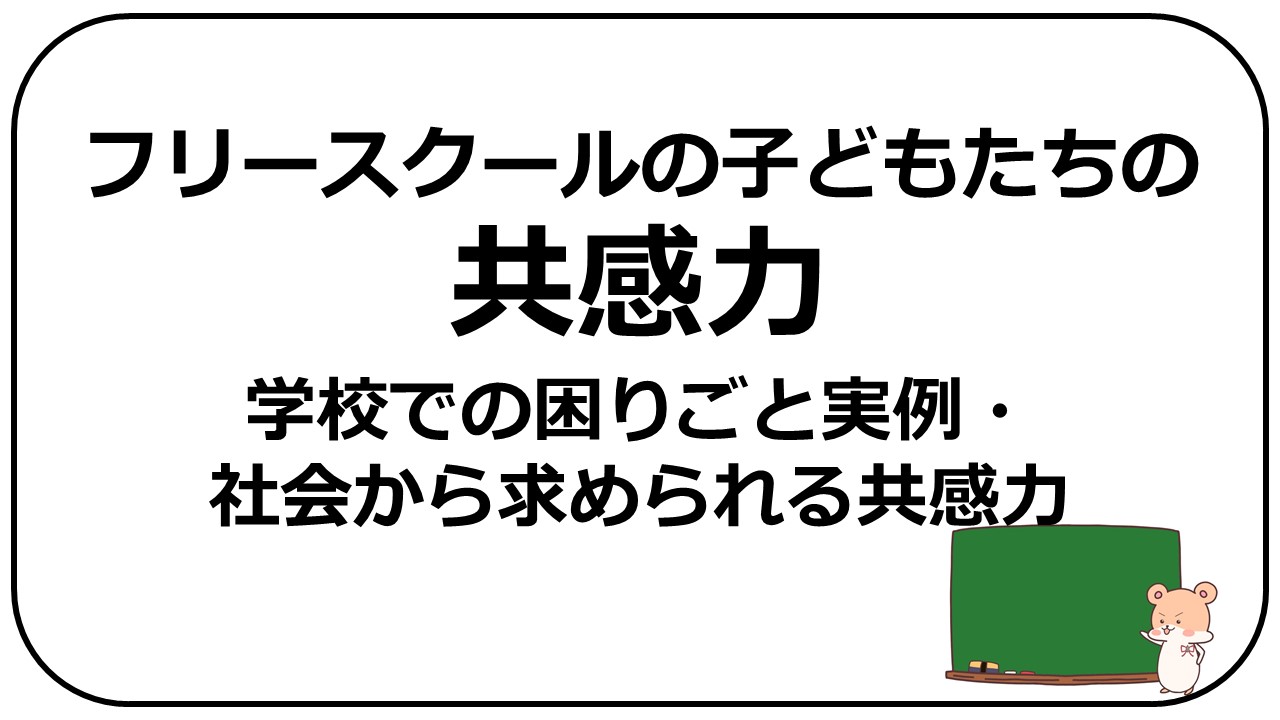はじめに ~オリンピック~
レイパスでも、東京オリンピックの話題が子どもたちからよく出てくるようになりました。夏休みに入ったこともあり、レイパスでの学習(主に勉強)時間にオリンピックを見ることもあります。
今までサッカーのサの字も出さなかった女の子が、「サッカー日本代表は、今日、勝つか引き分けで決勝トーナメント進出です。仮に負けても、1点差なら大丈夫です。2点差以上ついても、メキシコ対南アフリカの結果によっては、決勝トーナメント行けるかもしれないんですよ。例えば南アフリカが……」と熱く話してくれます。

ミーハーだと冷たい目を向けられることもあるけど、レイパスではほほえましく捉えているんだな。

「他人の結果なんて興味ない」と考える子どもたちも増えていますが、人の勝利を我がことのように喜ぶ力は、共感力だと考えており、レイパスでは大切にしています。
共感力が高い子の例
レイパスではラベルを貼りたくないので、あまり触れませんが世間で言われているHSP/HSC(Highly Sensitive Person/Highly Sensitive Child)に当たる子どももいると思われます。レイパスのスタッフは専門性をもって対応していますが、心持としては「優しくて思いやりのある子たち」くらいの認識です。
①小学校2年生の女の子
学校で先生が、クラス全体に対して少し厳しい口調で注意をした。
小学校2年生のクラスながら、全員がまじめに先生の方を向いて注意を聞いていた。
ただ一人、ある女の子だけは、ぼろぼろと目から涙を流して聞いていた。
学校の先生が、全体に対して行った指摘を、自分事として捉える力(共感力)が優れているのだと思います。その子は学校へ行きづらくなり、今はレイパスに週1~3回程度通っています。
②小学校6年生の男の子
小学校低学年の時から、なにをやっても人よりうまくできた。
自然と、班長などの役職を務めることが多かった。その時は、嫌だという気持ちはなかった。
しかし中学年・高学年と学年があがるにつれて、周囲の「班長やるやろ」「優しいから○○係やってくれるよね」という期待がしんどくなってきた。
「自分はできる子でもないし、優しくもない」と苦しみを吐露した。
自分が周囲から何を期待されているかわかりすぎてしまう(共感力が高い)ため、しんどくなってしまうのだと思います。この子も学校へ行きづらくなり、今はレイパスにほぼ毎日通っています。
フリースクールでの様子
上記例のように、共感力の高さゆえに学校になじめない子がフリースクールには多く在籍しています。またフリースクールは、その性質上異学年交流が活発です。毎日、些細なことでも異学年の子と関わりながら過ごしています。
そのため、上の学年の子が下の学年の子に優しく接する場面を本当によく見かけます。

下の子の勉強を見てくれたり、一緒に遊べるように工夫してくれたりするんだな。

ちょっとしたことですが、お弁当のふたを開けられなくて困っている子に気づいて、助けてくれたりもします。
他の人の気持ちや困りに敏感なので、助け合いが自然発生します。そのベースに共感力(おもいやり)があると考えられます。
共感力
それではこの記事でテーマにしている「共感」とはどういうことか、脳科学とモノガタリ(マンガ・小説)から考えてみたいと思います。
脳科学の観点から
ミラーニューロン
誰かに手をつねられて「痛いっ!」と感じた場面を考えます。そのとき、つねられた人の脳が活性化するのと同じ部分が、それを見ている相手の脳内でも同時に活性化します。
このような働きをする脳細胞を「ミラーニューロン」といいます。
さらに、見ている人の脳の中で、「危ないっ!」と思ったときに活性化される「扁桃体」が活性化することがわかっています。
さらにさらに、相手を「助けないとっ!」と感じるときに働く部位「中脳水道周囲灰白質」も活性化します。

他者の危機を見て自分のこととして感じたり、助けようと思う共感力の根本は、人間の脳の仕組みにあるんだな。
ベガス神経
脳と身体中の様々な器官をつなぐ神経を「ベガス神経(迷走神経)」といいます。
ベガス神経は、「共感や思いやりといった気持ち」と、「体内に起こる生理学的な現象」を関連づけているそうです。
つまり、人のために何かをすると、自分の健康リスクが抑えられるということです。そのように進化の中で人の脳や身体がプログラムされてきたと考えられています。
モノガタリの観点から
サンテグジュペリ『人間の土地』
人間であるということは、とりもなおさず責任をもつことだ。
人間であるということは、自分に関係がないと思われるような不幸な出来事に対して忸怩たることだ。
人間であるということは、自分の僚友が勝ち得た勝利を誇りとすることだ。
人間であるということは、自分の石をそこに据えながら、世界の建設に加担していると感じることだ。
サンテグジュペリ『人間の土地』
自分とは関係ないことにも悲しみ、仲間の勝利を自分の誇りとする、まさに共感力の話です。

共感力こそが、人間を人間たらしめていると考えられるんだな。
荒川弘『鋼の錬金術師』22巻
人間の知らないところで、ホムンクルス(錬金術師が生み出した人造人間)が暗躍します。ホムンクルスたちは、優秀な錬金術師(人柱)を集めて、ある壮大な計画を進めています。
ここでは、人柱候補の「アル」とホムンクルスの「プライド」が会話しています。
アル「ボク達を”人柱”といって必要としているみたいだけど、もしボク達が自分の身かわいさに国外逃亡してたら今回のお前達の作戦はおじゃんだ。ちょっと計画がずさんじゃないのか」
プライド「だが君たちはこの国に残りました。自分だけ良ければこの国がどうなっても良いという考えは持たず中央に闘いに来ました。それが貴方達人間なのです。我々は君達人間が持つその揺るぎない心を信用しています」

私はこの場面、泣きました。嬉しかったからです。
作者の荒川先生が、人間に期待してくれている。私はその期待に応えていかねばならないと感じました。
未来社会で活躍する子どもたち
旧社会=合理的経済人の損得勝ち負け社会
昨日までは、「いかに得するか」「いかに自分が幸せになるか」を各個人が追及する社会でした。その中で市場原理(神の見えざる手)が働き、社会全体が発展していくというモデルでした。
個人個人が自分の利益を追求することによって、神の見えざる手に導かれるかのように社会全体の利益にもなっている

ただし、アダムスミスは『道徳感情論』で、市場原理だけでは足りず、人の道徳感情が必要だと訴えてもいたんだな。
トリクルダウン理論からも関連したことが仮説として示されています。
富める者が富めば、貧しい者にも自然に富がこぼれ落ち、経済全体が良くなる
未来社会=共感社会
明日の社会は違います。今の子どもたちが活躍するのは共感社会です。
例えば、クラウドファンディング。実施するプロジェクトをネット上などで公開し、多数の人たち(群衆=crowd)から資金を集める仕組みで、近年実施例が急激に上昇しています。

レイパスでも実施し、多くの人からご支援いただいたんだな。
このクラウドファンディング、様々な形式がありますが多くの場合、支援に対してリターンがあります。しかしながら、「リターンで得するから応援する」のではなく「共感したので応援する」という意味合いが強いです。つまり、「損得」よりも「共感」が行動原理として一定の力を持ってきているのです。
今後この流れは強まります。企業も、もともとは「儲かる活動=社会貢献」でしたが、それだけでは足りなくなってきました。消費者が「共感」できなければ買わなくなってきています。
他者の気持ちに対して感度の高い、「共感できる人」が活躍できる社会へと変化してきています。

フリースクールでは、様々な学習を通して学校へ行けない子どもたちの才能(ここでは共感力)を伸ばしています。