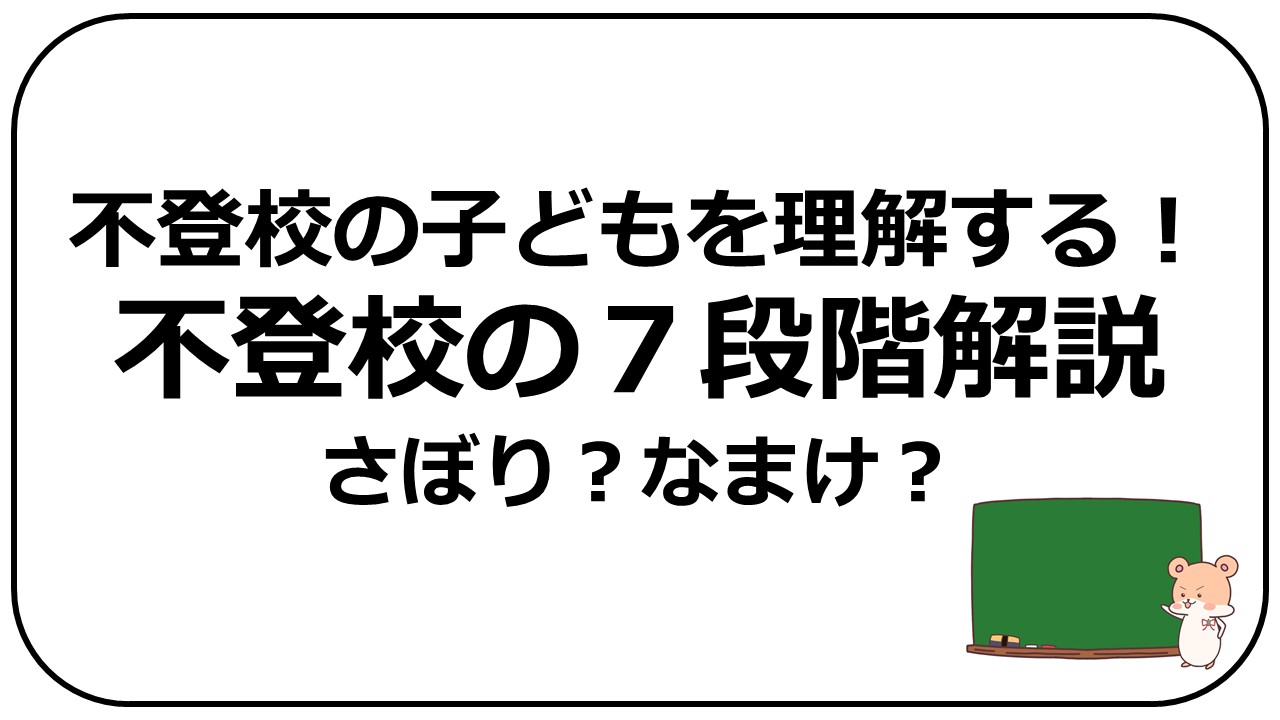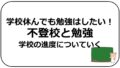はじめに

朝、しんどいというので学校を休ませました。
でもそのあとは、楽しそうにスマホを触ったり、ゲームをしています。

不登校支援をしているとよくある課題です。子どものことが心配だからこそ気になってしまいますね。
学校を休んで、スマホを触ってばかり…楽しそうにゲームをしている…というお悩みはよく伺います。
実際にレイパスを利用されている保護者からお伺いするのは以下のようなお声です
・本当にしんどかったのかわからない
・このままで将来大丈夫だろうか
・約束した勉強をしない
・さぼっている、なまけているように見えて、イライラする
・この状態がいつまで続くのか、先が見えず不安
・結局、何を考えているのかわからない

不登校の子どもたちの心の声に分け入ってみるんだな。
不登校の7段階
不登校の子どもたちと関わる大前提として、レイパスが大切にしているのは以下の2点です。
①一人ひとり状況は異なる
②ある一人の中でも、毎日状況は異なる

感覚的には、十人百色くらいなんだな。

その前提に立ったうえで、分析するためのモデルは役に立ちます。ここでは、コミュニティ総合カウンセリング協会が定めている不登校の7段階をご紹介します。
第一段階:不登校開始期
第二段階:悩み苦しむ時期
第三段階:エネルギー補充期
第四段階:エネルギー再活性化期
第五段階:再活動希望期
第六段階:リハビリ期
第七段階:社会復帰期
第一段階:不登校開始期
頭では「学校へいかなきゃ」と思っているのに、身体が「いきたくない…」と拒否反応を示している時期です。この時期は、周りはもちろん本人も単に体調が悪いだけだと思っています。学校が原因だとはっきりとしておらず、なにが原因なのかわからずもやもやしてしまいます。

この時期はとにかく身体の声に耳を傾けることが大切なんだな

最近は、身体症状が出たら無理せず休むという考えのご家庭が増えてきました。
第二段階:悩み苦しむ時期
苦しむ時期で、暴れたり怒鳴ったりして感情を発散することもあります。学校へ行かせよう、病院へ連れていこうなどとあまり多くのことを子どもに求めると、状況が悪化していくことが多いです。

一番身近な保護者が、状況に理解を示してゆっくりさせたり、話を聞くのが大事なんだな。

一方で、受け止める保護者(主にお母さん)が疲れてしまうこともあります。保護者が相談できる相手を見つけることも大事です。
第三段階:エネルギー補充期
一日中寝ていたり、真っ暗な部屋に閉じこもったりしています。脅したりすかしたり、お願いをしたりどんな声掛けをしても手ごたえが得られない時期です。1年2年と続くこともあり、保護者をはじめ支援者としても大変難しい時期です。

レイパスで関わっている子は、1日で復活する子もいます。1週間、1か月くらい必要な子もいます。

だれにでも必要な充電期間なんだな。
第四段階:エネルギー再活性化期
充電期間には、復活のタイミングを探している子もいます。この段階に差し掛かってくると、なにかしらの活動をはじめます。特に多いのが、スマホでゲームをしたり動画を見たりです。もちろん、「スマホゲームこそわが人生の生きがい」と思っている子もいるでしょうが、多くの子どもは手軽に暇をつぶせるからスマホを触っています。

保護者として理想の過ごし方ではないでしょうが、子どものエネルギーが出てきたことを前向きに捉えていきたいところです。
第五段階:再活動希望期
子どもの方から、「なにかしようかな」「○○してみたいな」などと言ってきます。飽きるまでゲームをさせ、この段階になると一緒にラーメンを食べにでかけたというひきこもり支援者の方もいます。興味のあることを探したり、助けたりしながら外の世界とつなげていく時期です。

当然、各段階まざっていたり、行ったり来たりを繰り返すんだな。
この5段階目までに1か月以上かかる子もいれば、1日という子もいるんだな。
第六段階:リハビリ期
この段階は不安定活動期ともいわれ、実際に活動し始めるものの以前と同じようには行きません。
しかし、学校の話題を出しても抵抗なく話せる子もいますし、自分から学校について話をしてくる子もいます。
その場合、少しずつ登校を促したり、学校と連携して通いやすい体制を模索します。例えば、別室登校やオンラインでの授業、通いやすい授業を選んで登校するなどです。

コロナの時期を経て、学校もオンライン対応などがんばってくれるところが増えてきているんだな。
第七段階:社会復帰期
安定して登校したり、社会との関りを持ちながら生活できる時期です。1日1日を大切にし、疲れた時の休み方を身に付けていくことも必要です。うまく休めるようになれば、上に見てきたような充電期間も少なくて済みます。

この時期の捉えも大切なんだな。これらの段階を子どもの成長過程として捉えれば、これからの人生での「転んだ時の起き上がり方」を身に付けたと考えられるんだな。
「さぼり」、「なまけ」なんだろうか?
苦悶の時期・充電期間かな?

このように、不登校の7段階から子どもを見つめなおすと少し考えも変わるかもしれません。身体に症状がでているのは本当です。ゲームをしているのも、身体の痛み・心の負荷をまぎらわせるためです。
そして、苦悶の時期・充電期間を越えれば子どもはまた動き出します。

パスカルが「人間のすべての不幸は、部屋の中でじっとしていられないことから起こる」と言っているように、なにかしたくて動き出してしまうのが人間なんだな。その結果が、不幸だとしてもだな。
フリースクールに通う子どもたちでも、調子の波があります。レイパスを続けて休んだ時などにも、レイパスは「ゆっくりさせてください」と保護者に伝えます。
子どもは、植物に例えられます。芽も、葉も、花も、実もすべて子どもたちは自分の中に持っています。子どもは可能性を実現させていく存在なのです。それほど多くのことを保護者が与えなくても、子どもたちは勝手に花を咲かせるのだと信じています。

お母さんたちに、もっと楽になってほしいんだな。

遅れた勉強のキャッチアップは、レイパスが全力でサポートします。
保護者にできること ①家をあけてみる
一方で、保護者の不安もわかります。が、そこを踏ん張って子どもと距離をとることに挑戦していただくことがあります。お母さんが、思い切って家をあけて子どもを一人にしてみることで、事態が好転する例もあります(当然、一人にしない方がいいこともあります)。

日中ずっと家で一緒にいると、どうしてもお互いしんどくなってしまうんだな。
保護者にできること ②勉強してみる

最後に、1つのエピソードをご紹介します。
その子は、一度も親から「勉強をしなさい」と言われたことがなかった。
その代わり彼が見ていたのは、仕事終わりの平日夜や休日に集中して勉強する父の背中だった。
彼にとって、勉強する背中はかっこよかった。憧れだった。
もちろん、彼も他の子と同じようにゲームもすれば、宿題をさぼることもあった。
それでも、最低限の勉強はしてきた。親に言われなくても。いや、言われなかったから。
彼は一度も「勉強しなさい」と言われることなく、大阪大学法学部へ合格した。